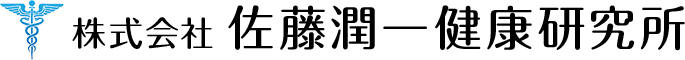産業医とは、事業場において労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師を言います。労働安全衛生法により、一定の規模の事業場には産業医の選任が義務付けられています。

産業医となるためには、事業場において労働者の健康管理等を行う産業医の専門性を確保するため、医師であることに加え、専門的医学知識について法律で定める一定の要件を備えなければなりません。厚生労働省令で定める要件を備えた者としては、労働安全衛生規則第14条第2項に次のとおり定められています。
日本医師会認定産業医は、次の1に該当します。
1.労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
2.産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
3.労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4.学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常勤勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者
5.前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
・各種健診(雇い入れ時、定期健診、夜勤者健診、特殊健診、海外赴任前・帰任時健診、その他)の判定業務
・健診結果に基づく就労判定
・面接実施と紹介状作成
・就労措置のための意見書作成
・職場巡視
・安全衛生委員会への参加
・長時間労働者への面接指導
・就業措置のための意見書作成
・健康診断や人間ドックの結果についての相談
・フィジカルやメンタルの症状や治療、受診についての相談
・高リスク者に対する面接指導
・職場におけるメンタルヘルス対策
・病院、クリニックなどの医療機関に関する最新かつ安心な情報の提供
・医療機関の紹介、必要時紹介状の作成は、医療機関の紹介に変更
・希望する医療機関への紹介状、診療情報提供書などを作成
・感染症をはじめ最新かつ正確な医療情報の提供
・健康コラムの配信
・生活習慣病、メンタルヘルス、睡眠やリラクゼーション、インフルエンザなど感染症、ハラスメント、その他
・スムーズに休職に入り治療に専念できること
・休職中、希望があれば主治医と連携して療養効果を向上、早期の復職をはかる
・復職のための準備を支援し、企業側との連携を行い、就労上の配慮などを検討
・無理がなく効率的な業務再開をバックアップするとともに、再発予防策の構築
・こころとからだに優しい健康レシピの紹介
・音楽、美術など芸術と健康についての情報の提供
・健康や医療に関する様々な問題に、オーダーメイドで対応
・1~49人:医師などによる健康管理(努力義務)
・50~999人:産業医(嘱託可)
・1000~3000人:産業医(専属)
・3000人~:2人以上の産業医(専属)
・一般の労働者:法定時間外労働が1か月に80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者が自ら申し出た時
・新たな技術、商品または役職の研究開発に従事する業務:休日労働も含め、1週40時間を超える労働時間が1ヶ月に100時間を超える労働者
・高度プロフェッショナル制度の対象者:健康管理時間(労働時間)が1週40時間を超える時間が1ヶ月に100時間を超える場合
(第六十六条の七)特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し医師又は保健師による保健指導を実施
(安全衛生則14,15条)産業医は少なくとも毎月1回作業場を巡視
(安全衛生則11条)衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場を巡視
(第十七条、第十八条)安全委員会、衛生委員会(又は安全衛生委員会)の設置義務
(安全衛生則23条)安全委員会、衛生委員会(又は安全衛生委員会)は毎月1回以上開催
(労働安全衛生法第14条第1項)
1.健康診断・その結果に基づく措置
2.長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
3.ストレスチェック、高ストレス者への面接指導・その結果に基づく措置
4.作業環境の維持管理
5.作業管理
6.上記以外の労働者の健康管理
7.健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進措置
8.衛生教育
9.労働者の健康障害の原因の調査、再発防止
・事業者や職場の責任者に意見を述べる権限
・労働者の健康を確保するため、緊急性が高い場合は、労働者に対する必要な措置を職場に指示する権限
(労働安全衛生法第14条第2項)
事業者は、労働時間に関する情報やそのほか必要な情報を産業医に提供しないといけない
1.健康診断後、過重労働面接後、高ストレス者面接後、において講じた事後措置の内容
(措置を講じない場合は、その理由)
2.月残業80時間を超えた労働者の氏名、当該機関
3.そのほか産業医が必要と認めるもの