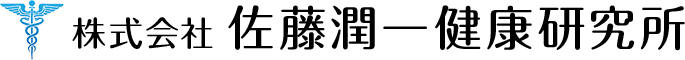従業員50人以上の事業所は、「衛生委員会」の設置義務があります。
「安全委員会」は、業種によって設置義務が従業員50人以上か、100人以上か分かれます。
安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならないときは、ひとまとめにして「安全衛生委員会」として実施することができ、ほとんどがこのパターンで開催しています。
人事・総務担当が資格をとることが多いです。
衛生管理者が産業医との連絡窓口になることも多いため、人望があり、職場のことをよくわかっている従業員で、役職者でない方が望ましいとされます。
また、資格を取得した方が退職や異動になる可能性も考慮して、複数名に受験させるようにしてください。
衛生管理者の資格試験は毎月実施されています。
衛生委員会や職場において、健康管理や衛生管理を目的に、産業医はじめ産業保健スタッフが従業員に向けて話す研修を実施します。
頻度・開催方法など法に定められているものではなく、健康教育の一環として企業・組織の自発的な要望により開催されるものです。
実施義務はありません。
企業からの要望で実施するものであり、決まった内容もありません。
まずは、「衛生講話とは何か」ということを企業と産業医とで確認することが大切です。
休職に対する法的な規定はなく、給料・タイミング・期間は企業の裁量(雇用慣行)によります。
期間は多くの場合、その社員の勤務期間より1カ月~3年程度であり、就業規則によって主治医判断だけでよい場合もあれば、産業医面談が必要な場合もあります。
企業には、安全配慮義務があるため、勤務によって本人の健康が損なわれる可能性がある場合は、声掛けをしなくてはなりません。
例えば、これまでにはなかったようなミスをする、居眠りや遅刻が多くなった等の様子が2週間程度続くような場合には、人事や産業保健スタッフが医療機関の受診を勧めます。こうした対応を怠ると、義務違反になる可能性があります。
最終的な決定は企業側が行うため、必ずしも従わなければならないわけではありません。
産業医はあくまでも医師としての意見を述べることが業務範囲です。
産業医の意見を基にして、企業がどのような措置をとるかを判断します。
その判断には産業医の意見だけでなく、主治医の診断書や本人の希望も考慮することが必要です。
復職できることを証明するのは本人であり、主治医の証明と本人の申し出が必要になります。
休職中に企業が本人と連絡やりとりをすることは可能ですが、復職を催促することはできません。
休職に入る際に、今後の連絡方法を確認し、定期的に診断書をもらうことを(できれば家族同席で)約束しておくことでその後の連絡をスムーズにとることができます。
主治医、産業医の双方の意見を聴いて判断するのは企業です。この溝を埋める方法としては、下記の3通りの方法が挙げられます。
①主治医に対して復帰後に労働者が従事する業務についての情報を伝え、それを基に判断してもらうよう依頼すること。
②具体的にどの程度の配慮をすることが必要かを主治医に明記してもらうこと。
③セカンドオピニオンとして主治医でも産業医でもない医師に判断をゆだねること。
必ずではありませんが、産業医又は事業場において産業保健活動に従事している医師が推奨されます。
必ずではありませんが、産業医又は事業場において産業保健活動に従事している医師が推奨されます。
いいえ。産業医が行うのは「診察」ではなく「面談」です。 産業医は「医師」ですが、法律上診断や治療は行えません。従業員への面談から疾病性の評価や判断を行います。事業者に「産業医意見書」を発行しますが、これは診断書ではありません。産業医は、この意見書を通じて就業区分を決定することが主な仕事です。
はい。意見書は会社に提出されますが、面談は原則産業医との1対1です。また、そもそも会社に言いずらい理由で悩まれている方が大勢いらっしゃるため、意見書に関してもお話の内容から伝えなければいけないものだけを抜粋し作成します。
「専門は何ですか?」とお聞きください。回答として「専門は産業医です」と返ってくれば良いと思います。多くの場合、内科、心療内科という回答が返ってきますが、産業医というもの自体が一つの領域です。産業医を専門としている先生に診てもらいましょう。
いいえ、必ず受診していただく必要があります。企業には健康配慮義務が、社員には健康保持義務が法的に存在しています。このケースの場合、健康保持義務違反として、社員の方を解雇する事由にも該当してきます。健康診断を受けなくても法的に問題ないのは原則自営業の方々のみです。
対応可能です。ストレスチェックの実施者はもちろん、実施事務業者様とも提携しているので、実施者としてお選びいただければ、システム会社さんを探す手間もありません。また、注意事項として、実施者を最優先で探すようにしてください。実施事務従事者(システム会社)を先に探すと、後々トラブルになることがあります。実施事務従事者の選択権は産業医にありますので、ご注意ください。
もちろん可能です。訪問時などに個別にご質問いただいても大丈夫です。
ありません。ただ労働契約法違反で、労働者本人または家族から民事訴訟を提起される可能性はあります。
【根拠条文】
労働安全衛生法第66条の八
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
労働契約法第5条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働安全衛生法違反で50万円以下の罰金となります。これは少しややこしいのですが、ストレスチェックを実施しなかった罰ではなく、ストレスチェックを実施したことを労働基準監督署に報告しなかったことに対する罰となります。
【根拠条文】
労働安全衛生法第66条の十
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
第100条
1 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
「就業規則の変更」をおすすめします。現実として、主治医と産業医の判断が違ってくることは多分にあり得ます。その際、判断は会社が行うことになりますが、裁判所の見解(判例)では産業医の意見に沿うことが望ましいとされています。
そのため、就業規則上にも明確に記載されておくことをおすすめします。
記載例は「主治医の復職可の診断書および産業医の意見書を基に復職の可否を判断する」などになるのではないでしょうか。就業規則の内容などについては、社労士さんや弁護士さんに1度ご相談されることをおすすめします。